創業からの70年 平成7~16年度
第6章さらなる飛躍を目指して

第4節管理部門の推移
1.総務部門
社内外への広報活動として、平成7(1995)年4月、ホームページを開設し、10年10月には、社内報「トーエネックニュース」を266mm×375mmの新聞様式からA4サイズ16ページのマガジンタイプに変更した。
11年10月、会社創立55周年を迎え、業務上および業務外死亡者51人の慰霊のため、五色山大安寺にて合同慰霊祭を開催した。
12年12月、社長への直接意見具申手段(現・コンプライアンスホットライン)を設置した。
16年10月、会社創立60周年を迎え、記念行事として講演会、合同慰霊式の開催、「60周年記念誌」の発行、記念配当などを実施した。
自己株式の市場買付
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、自己株式の市場買付を実施した。
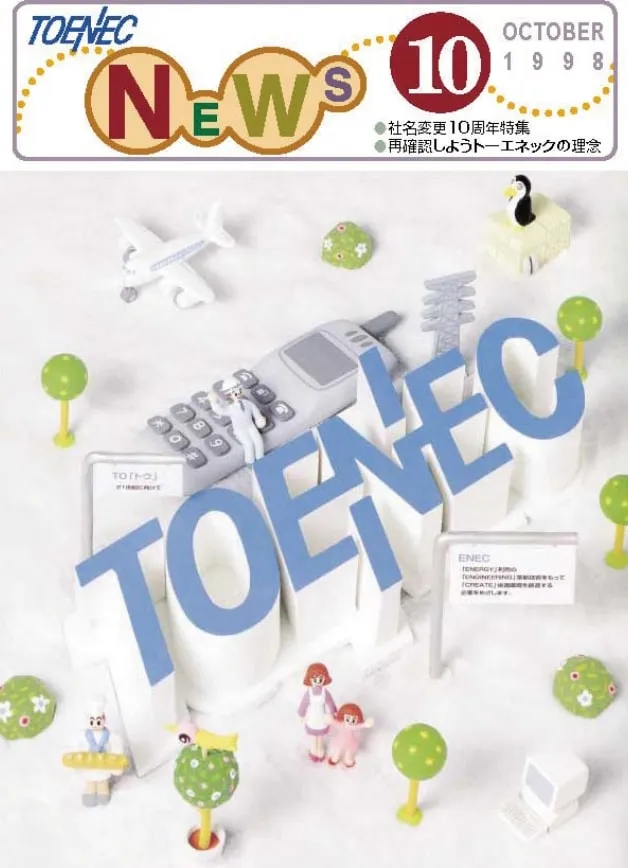
2.人事部門
人事制度の改定
平成10(1998)年は、就業規則に解職規程(無断欠勤が引続き14日を超えたときは、本人の意思表示があったものとみなし自動的に解職する)を追加した。同年、男女雇用機会均等法改正に伴い母性健康管理に関する措置を新設した。
11年には、委託工事において、予算工事量と施工能力に大幅な地域格差が生じたことから、技能職従業員の有期転勤(6カ月)を実施した。また、停電時間の短縮および工事規模の減少などにより、委託工事における時差勤務A(所定勤務時間6時間)を廃止した。
労働基準法および育児・介護休業法改正に伴い、深夜業の制限に関する措置の新設およびパートタイマーの年休付与日数を改定した。14年の育児・介護休業法改正では、時間外労働の制限および深夜業の免除の制定、および育児期間を満1歳未満の生児の育児を必要とする者から満3歳へ変更した。
12年は、年末年始の休日について、中部電力・官公庁をはじめとする得意先と休日を合わせ営業強化するため、12月30日~1月4日から12月29日~1月3日に変更した。
13年は、定年退職後の再雇用制度を制定した。対象者および採用基準は、定年退職者で再雇用を希望し、心身とも健康で勤務状況が良好であり、担当職務遂行に対する意欲と能力を有する者のうち、会社が必要とする者とした。他にも配電部門では、「班長」から「作業長」への名称変更、「主席作業長」職位の新設など、役割・職責にふさわしいやりがいにつながる技能職系職位体系に見直しを図った。
14年には、セクシャル・ハラスメント防止に関する規程を就業規則に明記し、15年には、1カ月単位の変形労働者時間制取り扱いを制定した。
福利厚生制度、その他制度の改定
平成16(2004)年度には、企業年金制度を将来にわたって安定維持するため、国の老齢厚生年金の代行部分を返上(代行返上)し、トーエネック企業年金基金への移行を図った。さらに、健康管理を含めた従業員情報の一元管理を図るため、保健衛生業務を人事部の業務分掌とした。
トーエネック技術短期大学校の廃止
平成4(1992)年に開校したトーエネック技術短期大学校は、1期生28人、2期生29人、3期生22人、4期生28人、5期生26人と、5期連続20人以上の入学者数を維持していたが、その後、6期生15人、7期生19人、8期生13人、そして9期生は11人と20人を下回る推移となった。長期不況に伴う建設市場の縮小などにより経営環境は非常に厳しく、採用抑制などによる人員削減が避けられない状況であったなど、設立当時と採用環境が大きく変化したため総勢191人の技術者を輩出し、14年3月31日をもってトーエネック技術短期大学校を廃止した。15年3月14日に、教育センター敷地内において、記念碑の建立が行われた。

3.安全・環境部門
労働安全衛生の推進
平成7(1995)年6月、労働災害防止意識高揚のため安全表彰制度を改正し、社長による連続無災害表彰および本部長・支店長表彰を追加した。
9年3月、道路交通法の一部改訂に伴い、「車両運行管理要則」の社有車両の日常点検、運行管理に関する条項を改定した。
14年7月、安全・環境部の安全課と衛生課の業務分掌を見直して、安全・衛生グループに組織改定した。また、労働安全衛生法および労働安全衛生規則の一部改訂に伴い「安全衛生管理規程」をはじめとする労働安全関係要則類の全面改定を行った。また、「緊急全社安全大会」を実施し、愛知労働局長、建設業労働災害防止協会愛知県支部長および中部電力支配人人事部長を来賓に招き、安全衛生活動の活性化および労働災害防止の徹底を図った。
同年12月、労働安全衛生管理運営における国際化ISO規格に対応すべく、安全衛生管理規程に労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS:Occupational Safety and Health Management System)を追加した。
15年1月、社長が安全衛生方針を制定し、全従業員に表明した。
16年4月、株式会社トーエネックサービスの安全衛生・環境コンサルタント事業拡大に伴い、トーエネックサービス安全環境事業部による監査養成を開始した。
安全行事関係
平成9(1997)年1月、新春安全祈願を行っている犬山市の成田山名古屋別院大聖寺の境内山門階段に社名入り石板を寄進した。
10年3月、殉職者慰霊碑がある五色山大安寺の本堂建立に伴い、社名入り青銅鋳物製八角灯篭一対を寄進した。
環境関係
平成11(1999)年4月1日に全社の環境保全に関する計画・実施および全社の総括業務担当部署として、環境課を新設し、部署名を安全衛生部から安全・環境部に変更した。環境課の主な業務として、環境保全活動を適確に実施し、企業としての社会的責務を果たす環境マネジメントシステム(EMS)のPDCA手法を各部署の業務に定着させ、EMS活動を組織総合力発揮のツールとして活用することでEMS業務の改善・効率化を図っている。
同年9月には「環境基本方針」を制定し、翌年1月には安全かつ快適な循環型経済社会の構築を目指す「環境パートナーシップ・CLUB」会員となった。
14年11月には、ステークホルダーとのコミュニケーションや地域での情報発信などに活用するため、環境活動をまとめた「環境レポート」第1号を発刊した。
環境マネジメントシステム
平成12(2000)年4月から第1次EMS活動部署として、名古屋支店を対象にEMS体制を構築して運用を開始した。9月には半田、瀬戸営業所が外部審査機関による審査を受けISO14001認証を新規取得した。また、10月からは第2次EMS部署として、本店電力本部および名古屋本部を対象にEMS体制を構築して運用を開始し、13年3月には外部審査機関による審査を受けISO14001認証を取得した。同年10月からは名古屋支店を除く各支店および教育センターでEMS体制を構築し運用を開始した。
外部認証を取得しない事業場については「EMS社内認証制度」を導入した。これは、社内審査によりISO14001に適合している事業場を認証するものであった。
14年4月から第3次EMS活動部署として、本店本館、東京本部、大阪本部でEMS体制を構築し運用を開始したことにより、全社の全事業場でEMS活動が整った。
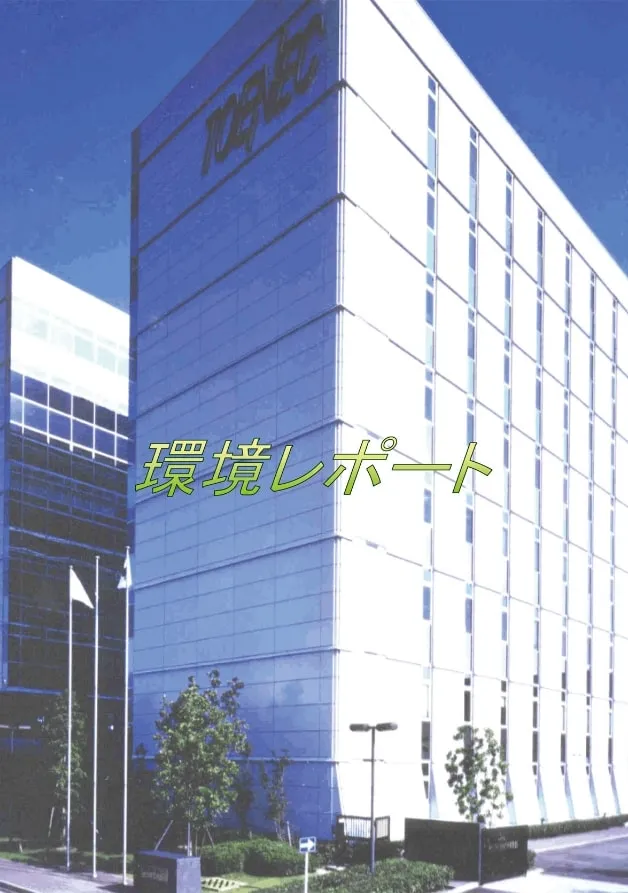
4.経理部門
会計制度の推移
平成8(1996)年度、「外貨建取引等会計処理基準」が改正され、為替予約などに対する会計処理について新たな基準が追加された。
10年度、新連結決算制度が翌年度から導入(個別から連結中心主義へ変更)されるのに伴い、改正前の連結財務諸表規則に基づき連結財務諸表を作成した。また、有価証券の評価基準および評価方法における低価法の適用に当たって、従来は切放方式によっていたが、洗替方式に変更した。
11年度、改正後の連結財務諸表規則に基づき連結財務諸表を作成した。
12年度、「退職給付に係る会計基準」を適用し、退職給与引当金および企業年金制度の過去勤務債務などにかかわる未払金は、退職給付引当金に含めて表示した。期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、1年以内に満期が到来する有価証券は流動資産の「有価証券」として、それ以外は投資などの「投資有価証券」として表示した。
13年度、従来、資産の部に計上していた「自己株式」は、財務諸表等規則の改正により資本の部の末尾に表示した。
14年度、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」が14年4月1日以後開始する連結会計年度にかかわる連結財務諸表から適用となった。
16年度、「固定資産の減損に係る会計基準」および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用し、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めない場合は、減損処理を行い、帳簿価額を減額することとした。引当金の計上基準が厳格化されたことにより、将来の工事損失に備えるため、工事損失が確実に見込まれる場合、合理的な工事損失見込額を「工事損失引当金」として当期から計上することとした。
子会社などの状況
平成9(1997)年度、株式会社トーエネックサービスを連結子会社として連結経営指標などの開示を行った。
5.情報システム部門
システム開発・再開発
オープン化に対応した開発の推進
一層の業務処理効率化を目指し、クライアント・サーバ型システムの開発を基本とした。
・営業情報システムの開発(平成7〈1995〉年10月4日運用開始)
・人事情報システム(第2次)の再開発(平成9年4月1日運用開始)
・リース機器管理システムの開発(平成9年4月1日運用開始)
・配電工事システムの再開発(平成10年3月23日運用開始)
・商事販売管理システムの再開発(平成11年4月1日運用開始)
・配電資材システムの再開発(平成11年7月21日運用開始)
・業務連携支援システムの開発(平成13年9月21日運用開始)
一般工事にかかわる基幹システム再構築計画
平成12(2000)年6月12日には、企画室、営業本部と共同で「基幹システム再構築基本構想」を策定し、7月1日付で情報システム室に基幹システム再構築プロジェクトを設置した。先行開発していた営業情報を含め、一般工事にかかわる工事管理、施工支援、積算、外注管理、購買の5システムを対象とし、開発に着手した。
・営業情報システムの再開発 (平成13年10月13日運用開始)
・工事管理システム(第1期計画)の開発 (平成15年10月23日運用開始)
また、一般工事と同種の業務プロセスをもつ配電部門の配電拡大工事システムの開発を並行して実施した。
・配電拡大工事システムの開発 (平成16年4月1日運用開始)
情報システム基盤の推進と整備
情報システム基盤の整備
平成7(1995)年3月、新たに「情報設備形成方針」を策定し、標準的なネットワーク(TCP/IP)への移行、メーカーに依存しないオープン化・ダウンサイジングなどにより情報処理の効率化・情報共有化・設備コストの削減を目指した。7年10月に運用を開始した営業情報システムから適用し、各支店にLAN設備を整備してサーバ機(UNIX)とパソコン(Windows3.1)端末によるシステムを構築した。9年4月運用開始の人事情報システムでは、営業所にLANを整備しネットワークを展開した。これにより将来につながる社内ネットワークの基礎を構築していった。
EUCの推進
従業員一人ひとりの情報活用を目指し、パソコン導入の推進とともに情報リテラシー向上のためEUC(エンドユーザーコンピューティング)教育を進めた。
イントラネットの運用開始
社内メールシステムは、平成8(1996)年10月から役員・幹部社員を対象に開始し、順次利用者の範囲を拡大した。非定形業務の効率化・高度化を狙いに、全社レベルのコミュニケーション効率化と情報共有を図るイントラネットシステムを構築し、電子メール、掲示板、施設予約、文書ライブラリを対象として13年9月から本格運用を開始した。
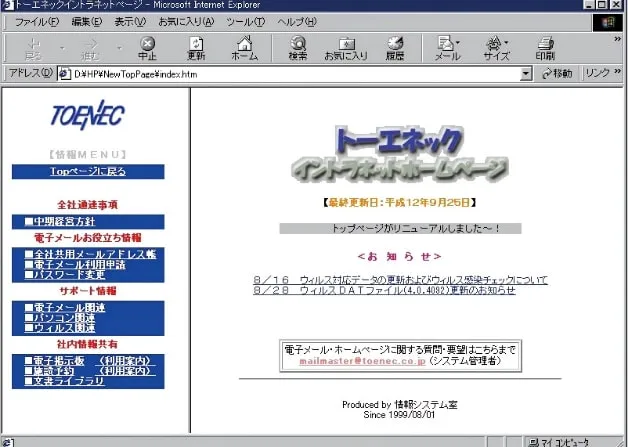
6.資材部門
平成9(1997)年7月、営業本部から購買部を分離し、資材部へと改組し、資材課、購買課を設置した。
10年度には、営業部門のコスト削減活動と連携し、材料の早期査定による集中購買の利点を活用し、「一般工事主要機器の価格査定取扱い」の運用を開始した。
11年10月に、配電資材システムの再構築に合わせ、貯蔵品配給システムとのデータ連携によって、業務処理の効率化を図った。12年10月、移動体基地局向け材料の単価契約方式を採用し、業務の効率化を進めた。
15年7月に、資材調達の強化策として、支店購入権限を縮小し、本店集中購買による効率運営を図り、翌年7月には、支店総務部門のスリム化計画に基づき、工事材料のコスト削減、商品販売の強化を図るため、支店購買課を資材グループに改組した。


