創業からの70年 平成17~25年度
第7章苦難を乗り越えて

第1節経営概況
1.当社を取り巻く経営環境
バブル経済の崩壊後、日本経済は「失われた10年」と称されるほど低迷した。21世紀に入った平成13(2001)年度はIT不況を迎えたが、翌年を境に景気は好転し、14年2月から19年10月までの長きにわたる景気回復局面が続いた。戦後最長記録となる69カ月間にわたる好況は、「いざなみ景気」と呼ばれた。この景気回復の背景には、アジアを中心とする新興国需要が拡大したことに加え、アメリカによる過剰投資が影響したとされる。
しかし、19年9月、アメリカの住宅ローン「サブプライムローン」の破綻をきっかけに、アメリカの景気が悪化したことから信用不安が広がり、世界の経済にも影響が及んだ。さらに20年9月、大手投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻を契機に金融危機が高まり、「リーマン・ショック」という世界同時不況に陥った。この時期を境に、日本経済は再び不況に突入した。この状況を経て、21年後半は外需とエコカー補助金、エコポイントなど、リーマン・ショックの影響に対して政府から各政策が打ち出され、日本経済は持ち直したかに見えた。しかし、22年は急激な円高が消費マインドを低下させ、投資の抑制や雇用情勢の悪化により厳しい状況で推移した。
23年は3月11日に発生した宮城県沖を震源とするマグニチュード9.0、国内観測史上最大規模の東日本大震災により、サプライチェーンの寸断や東京電力福島第一原子力発電所で深刻な事態が発生するなど厳しい状況となった。
24年は復興需要で立ち直りつつあったが、欧州債務危機や電力の供給制約など、厳しい状況は続いた。同年12月、第2次安倍内閣が発足し、「アベノミクス」と呼ばれた新たな経済政策、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の3本の矢を柱とする政策により、日本経済は円安・株高を伴った景気回復基調となった。25年にはデフレからの早期脱却と民需主導の経済成長により、しっかりとした経済再生の足取りとなった。
国内では、リーマン・ショック以前から公共事業への投資縮小が続き、建設業界の業容も伸び悩んだが、震災復興需要や企業マインド改善、補正予算による政府建設投資などで増加基調となった。一方、電力業界では7年12月の電気事業法改正に伴い、電力事業の自由化が進んだほか、中部電力の設備投資抑制に伴い、同社からの受注が一層厳しくなるため、当社は首都圏を中心に中部電力以外の顧客からの受注を拡大する新たな経営戦略が必要となった。また、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(新制度)が24年7月にスタートしたことにより、太陽光発電設備などの設置が加速度的に進んだ。
2.経営機構の改革
経営環境の変化に迅速に対応し、ステークホルダーから信頼される経営を目指して、平成17(2005)年6月にはコーポレートガバナンス(企業統治)のさらなる強化を図るため、取締役の任期を2年から1年に短縮し、取締役の員数を25人以内から15人以内に変更した。
3.野田泰弘社長の就任
平成17(2005)年6月、中部電力の野田泰弘副社長が12代目社長に就任した。中部電力では、営業部門の経験が長く、同社取締役、常務などを歴任し、15年に副社長に就任した。なお、山田久雄前社長は相談役に就任した。
11年3月期に売上高の約48%を占めていた中部電力からの受注額は、同社の設備投資抑制により、17年3月期に約39%まで落ち込んだ。この厳しい経営状況を受けて、野田社長は中部電力のエネルギー提案グループと協力し、省エネや二酸化炭素排出量削減などの「ソリューション事業」をさらに強化するとの方針を打ち出した。他社にはない技術力と経験を生かし、ソリューション事業を拡大することで、中部電力以外からの受注増にも力を注いだ。
4.中期経営計画(2006~2008年度)の策定
平成18(2006)年3月、3カ年の中期経営計画(2006~2008年度)を策定した。当社は「持続的な成長戦略の推進」をスローガンに、次のような基本戦略、経営方針を掲げた。
〈基本戦略〉
- お客さま第一主義に徹し、総合設備企業として幅広いお客さまのニーズに応え、お客さまに信頼され、選ばれる企業を目指す。
- 会社の競争力を維持・強化するとともに、収益力の向上・財務体質の強化を図りながら、企業価値の向上に努める。
- 中部電力グループ目標の達成に確実に寄与する取り組みを展開する。
- 創造性と個性豊かな人材の開発を推進し、活力あふれる職場づくりを進める。
〈中期経営方針〉
1. 収益向上を目指した受注戦略の推進
(1)コア事業の受注強化・元請工事の拡大
(2)コスト競争力の強化
(3)エネルギーソリューション事業の強化
(4)新規・新領域事業の開拓
2. 経営効率の向上
(1)全部門、事業場営業利益確保体制の構築
(2)固定費の削減と経営資源(人・物・金)の再配備
(3)組織総合力の強化
3. 経営管理体制の整備
(1)CSRに対する取り組みを強化
(2)管理体制の強化
(3)当社グループ経営管理体制の強化
4. 企業風土の改革
(1)人材の育成強化
(2)活力ある職場づくり
5.内部統制システムに関する基本的な考え方と体制づくり
平成17(2005)年7月、会社法において、内部統制に関する取締役会決議が義務づけられ、整備・開示が求められた。
18年5月、株主、お客さまをはじめとするステークホルダーから信頼・選択される企業となるため「創造と挑戦を軸に事業を展開し、社会・顧客の信用を得て、個性あふれるエクセレントカンパニー」を目指すことを経営の中心に据え、「会社の業務の適正を確保するための体制」を次のように決議・整備した。
1.経営管理に関する体制(業務執行に関する体制、内部監査に関する体制)
2. リスク管理に関する体制
3. コンプライアンスに関する体制(社内体制、中部電力グループ体制)
4. 監査に対する体制
5. 企業グループの業務の適性を確保するための体制(親会社との関係にかかわる体制、トーエネックグループの体制)
6.財務報告にかかわる内部統制の整備と対応
平成18(2006)年6月、証券取引法を改正した金融商品取引法において、20年度から、財務報告にかかわる内部統制について評価した「内部統制報告書」を作成し提出することが求められた。それを受け、運用に向けて財務報告に関する重要な業務プロセスを可視化し、確認・評価できる仕組みを作成した。
7.中部電力グループ「CSR宣言」の導入
中部電力が平成20(2008)年3月に制定した「中部電力グループCSR宣言」および「中部電力グループ社会貢献基本方針」に賛同し、採択した。
8.トーエネックグループによるコンプライアンスの強化
平成20(2008)年7月、コンプライアンス宣言、危機防止のための行動基準〈7つのモノサシ〉(14年制定)、コンプライアンス推進体制、推進の進め方などを収めた「トーエネックグループ・コンプライアンス指針」を策定し、コンプライアンス推進活動を刷新した。
この指針の策定により、社長を委員長としたコンプライアンス推進委員会、その補佐会議体であるコンプライアンス審議会およびコンプライアンス業務運営部署である事務局の設置、コンプライアンス施策実施のためのコンプライアンス責任者およびコンプライアンスリーダーの配置、役員・従業員などを対象とした教育啓蒙活動の実施、コンプライアンスにかかわる相談のためのコンプライアンスホットラインの設置などから成る現在のコンプライアンス推進体制を確立した。
「コンプライアンス宣言」
私たちトーエネックおよびグループ会社は、
「社会のニーズに応える快適環境の創造をめざす」「未来をみつめ独自性を誇りうる技術の展開をめざす」「考え挑戦するいきいき人間企業の実現をめざす」の3つの経営理念のもと、“総合設備企業としての社会的責任を果たす”べく、基本方針と行動基準により全社一丸となってコンプライアンスの確立に努めます。
9.越智洋社長の就任
平成21(2009)年6月、中部電力の越智洋副社長が13代目社長に就任した。なお、野田泰弘前社長は顧問に就任した。
社長就任に当たって越智社長は当面の課題として、一定の受注高を確保することと、選別受注のバランスをとることを重視した。また、「厳しい環境下においても、持続的な成長戦略の足固めを行い、強靱な企業体質への転換を実現すること」と述べた。
10.中期経営計画(2009~2011年度)の策定
平成21(2009)年4月、3カ年の中期経営計画(2009~2011年度)を策定した。「強靭な企業体質への転換~持続的成長戦略の足固め~」をテーマに掲げ、基本戦略、経営方針、数値目標を定めた。
〈基本戦略〉
- 「お客さま満足」を常に意識し、お客さまの立場に立ったきめ細かなサービスの提供を徹底し、選ばれる企業を目指す。
- 中部電力グループ、さらにはトーエネックグループ総合力の向上を目指した取り組みを確実に展開する。
- 会社の競争力となる総合力強化のために、一人ひとりが会社全体を見わたす幅広い視野をもち、全体最適の取り組みを展開する。
- 会社の成長の原動力である提案、営業、管理・指導などの総合力を備えた現場力の強化を図る。
- 対話重視のいきいきとした活力あふれる職場づくりを推進する。
〈中期経営方針〉
1. 収益向上を目指した受注戦略の推進
(1)コア事業の受注拡大と元請工事の拡大
(2)新規・新領域事業の開拓
2. 経営効率の向上
(1)徹底したコストダウン施策の推進
(2)経営資源の再配分
(3)キャッシュフロー経営の推進
(4)IT戦略の推進
(5)部門・本支店間のコミュニケーション増進
3. 経営管理体制の強化
(1)信頼される企業づくりの推進
(2)当社グループ経営管理体制の強化
(3)リスク管理の強化
4. 人材の育成強化
(1)人材の育成強化
(2)現場力の強化
(3)活力ある職場づくり
11.緊急収支対策の実施
リーマン・ショックによる影響は世界同時不況へと発展し、平成21(2009)年は当社にとって極めて厳しい経営環境が想定された。こうした中、中期経営計画を踏まえながら体質強化を進め、持続的な成長に結び付ける姿勢が求められた。全社で危機意識を共有し、また直面する難局を打開するため、21年8月に緊急収支対策を実施した。
12.コンプライアンス基本方針の制定
平成20(2008)年4月以降、コンプライアンス推進委員会を核にコンプライアンスを推進する現在の体制が確立され、さらに、21年7月に法務室が新設され企業法務とコンプライアンス活動の強化を図った。24年5月、従業員に期待するコンプライアンス行動を明示し、会社としてのコンプライアンス行動の明確化を目的として、当社およびグループ会社のコンプライアンス宣言の一部修正およびコンプライアンス基本方針の制定を行った。
〈コンプライアンス基本方針〉
私たちトーエネックおよびグループ会社は、コンプライアンスに関する基本方針を以下のとおり定めます。
- コンプライアンスの徹底:法令・社内規程類・社会規範を遵守します。
- 公正・誠実な企業活動:お客さま、協力会社、仕入業者、地域の皆様の信頼を高め、公正・誠実な企業活動を行います。著作権、特許権等の知的財産権を尊重します。
- 適正な情報管理・公開:情報の取り扱いは厳正に、情報公開はタイムリーに行います。
- 健全な企業風土の確立:人権を尊重し、健全な企業風土をつくります。
- 適正な財務会計:企業会計の法令・基準に準拠し、適正な内部統制のもとで貸借対照表、損益計算書等の財務諸表の適正性を高めます。
- 公正な行動:利益相反行為、社会通念に反した金銭物品等の提供と受領を行いません。反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨みます。
- 環境の保全:地域環境の保全に努めます。
- 安全・衛生、保安の確保:労働安全・衛生、および保安の確保・維持に努めます。
13.東日本大震災への復旧対応
平成23(2011)年3月11日、東北地方で発生した大地震と、その直後に太平洋沿岸を襲った巨大津波は東北から関東にかけて、未曾有の被害をもたらした。当社は全部門をあげてライフラインや民間設備の復旧対応に当たった。
配電部門では、震災から2日後の3月13日、東北電力の要請を受けた中部電力の指示のもと、総員138人、車両65台で現地へ赴いた。
情報通信部門は同月12日、大手携帯電話事業者からの要請を受け、4人が宮城県に向かった。その後12人体制で、津波被害が大きかった宮城県北部から岩手県内において、基地局の不具合により携帯電話が不通になった被災地域に移動基地局を設置し、通信状況を維持すべく復旧作業を行った。
内線・空調管部門では、営業本部・東京本部が被災地に工場や事業所を構えるお客さま設備の仮復旧対応に当たった。震災直後の要請事項では、緊急発電機の手配、漏電遮断器の不具合対応、設備機器の落下防止、温水器の点検、キュービクル・ケーブルの取り替え・設置などが多かった。資材不足や燃料などの課題も考慮し、お客さまとともに復旧作業を進めた。
なお、同年5月、日本赤十字社、仙台市および郡山市などに総額約4,500万円の義援金を寄付した。この義援金は当社およびグループ会社に加え、役員、従業員、家族、協力会社から寄せられた募金を含めたものである。


14.改正省エネ法「特定事業者」の指定
省エネ法の改正(平成20年5月)に対応するため、平成22(2010)年7月に経済産業省中部経済産業局へ「エネルギー使用状況届書」を提出し、同年9月に「特定事業者」の指定を受けた。これによって、会社全体としてエネルギー削減計画を策定し、実施していくことが義務付けられた。同年11月には、「エネルギー管理統括者」「エネルギー企画推進者」を専任するとともに、定期報告書、中長期計画書を提出した。
省エネルギー対策の一策として、電力消費量、CO2の削減を目指し、空調・給湯・受電設備を高効率機器に取り替え、事務所照明器具をLED照明に変更した。
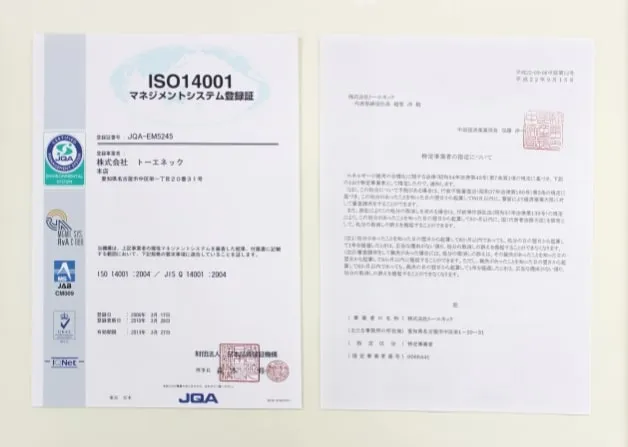

15.大震災後の中期経営計画(2012~2013年度)の策定
東日本大震災に伴う原子力発電の停止が相次ぎ、電力業界をはじめ経済の先行きが不透明になったことから、平成24(2012)年4月には、従来は3カ年計画であった中期経営計画を、2カ年計画(2012~2013年度)として策定した。この2年間を将来の成長に向けた企業体質強化のための好機と捉え、「お客さま満足度と従業員満足度の向上」を最優先に取り組むこととした。基本方針として「将来の成長を目指した事業基盤整備」を掲げ、次のような重点方針を定めた。
〈重点方針〉
1. 従業員自らが考え挑戦する企業風土の醸成
2. 組織総合力の向上を目指した体制強化
3. 安定した利益を確保するための体制構築
厳しい事業環境のなか、将来の成長を目指した事業基盤の整備に重点を置いた。従業員の意識改革、新たな教育体系の構築など人材育成の強化を進めるとともに、将来の成長市場と見込む省エネサービス、海外事業、情報通信などの分野で開拓を目指すこととした。
16.キャッチフレーズ、マスコットキャラクターの制定
平成25(2013)年4月から2カ月間にわたって、マスコットキャラクターを一般公募し、同時に「10年後、理想のトーエネックになるために」とのテーマで当社のキャッチフレーズを社内公募した。マスコットキャラクターには、全国から562作品が寄せられた。社外の特別審査員を含めて審査した結果、福岡県在住の吉永高規氏の作品が最優秀賞に選ばれた。キャラクター名は「つながルン」で、電気設備や情報通信設備などのインフラで、人と街をつなぐことをイメージ化したもの。25年9月から、広告やCMなどで使用を開始した。
また、キャッチフレーズには、155作品が寄せられた。審査の結果、古川哲次静岡支店総務部長の作品「“快適以上”を創造する会社」が最優秀賞に選ばれ、そのフレーズを補作して、「快適以上を、世の中へ。」との新キャッチフレーズが誕生した。この言葉に、当社の経営理念である「社会のニーズに応える快適環境の創造をめざす。」と従業員一人ひとりが常に意識し、快適のさらに上をゆく新しい価値を社会に提供していく決意を集約した。また、「快適以上」の新しい価値を、お客さまや地域の皆さまに提供することで、ともに発展し、未来につなげたいとの思いを込めた。
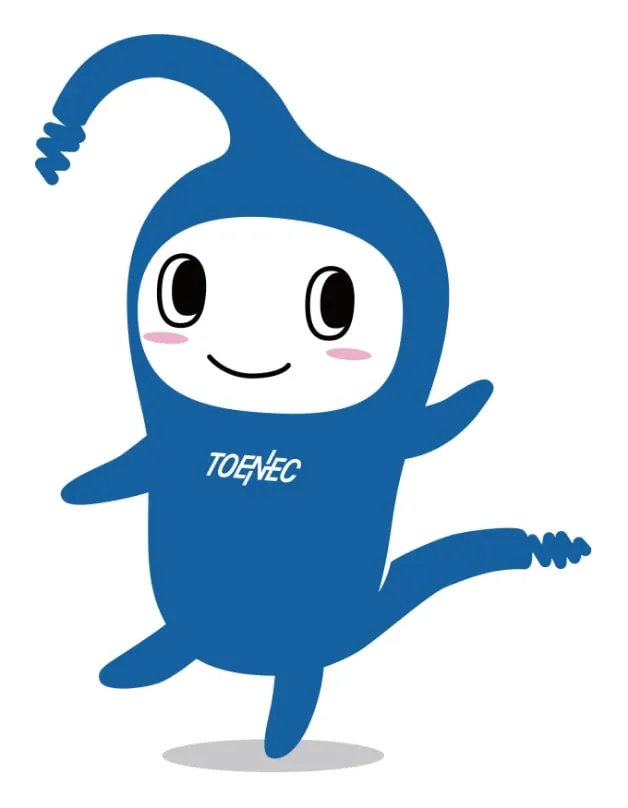
「つながルン」

17.大規模地震への対応
平成24(2012)年10月、「事業継続計画(BCP)」を策定した。東海・東南海・南海地震および首都直下型地震などの大規模地震発生時に、重要な業務を中断することなく、または中断を最小時間に食い止め、可能な限り短時間で業務を再開するための計画であり、重要事項は次のとおりである。
(1)従業員などの安全確保を最優先させる
(2)中部電力グループ会社として電力安定供給の早期復旧を図る
(3)お客さまの被害状況を早急に確認し、復旧に対応する
18.中期経営計画(2014~2016年度)の策定
平成26(2014)年3月、3カ年の中期経営計画(2014~2016年度)を策定した。基本方針として「現状からの脱却と明日への挑戦」を掲げ、次のような重点方針を定めた。
〈重点方針〉
1. 一般工事の拡大による売上高・利益の最大化
(1)提案型営業や施工営業などの対面営業を強化し、お客さまニーズを先見的に把握し他社との差別化を図る。
(2)太陽光発電関連工事については、確実な受注確保を目指すとともに、これを活用したお客さまとの関係強化を図る。
(3)成長が期待できる各分野における将来の市場性を評価し、事業拡大を推進する。
2. 電力関連工事における生産性のさらなる向上
(1)電力の事業環境の変化に対応すべく、生産性のさらなる向上とコスト削減を徹底する。
(2)厳しい経営状況下においても引き続き電力の安定供給の負託に応えていく。
3. 聖域なき効率化の推進
(1)工事原価および販管費の圧縮を徹底し利益体質強化を図る。
(2)材料費、外注費をはじめとして事務用品、コピーの類にいたるまで、あらゆるコストについて聖域を設けず効率化を推進する。
(3)雇用延長等を踏まえ要員の最適配置を図るとともに、従業員一人ひとりの知識と経験を最大限に活用する。
4. 企業風土の変革への挑戦
(1)企業の存続にはお客さまや社会からの信頼が不可欠であり、コンプライアンスの徹底と安全・健康意識の高揚を図る。
(2)効率化の推進は従業員に痛みの伴う変革を求めることにもなるため、一人ひとりが現状を正しく理解し自ら何ができるかを考え挑戦する風土づくりを促進する。
(3)現場の声を吸い上げる仕組みを強化し、風通しの良い職場を醸成するとともに、部門間・部署間でのコミュニケーションを活性化させ、オールトーエネックとしての一体感を高める。
(4)従業員個々の挑戦意識を促すため、キャリア開発制度等の人事諸制度を着実に推進する。


